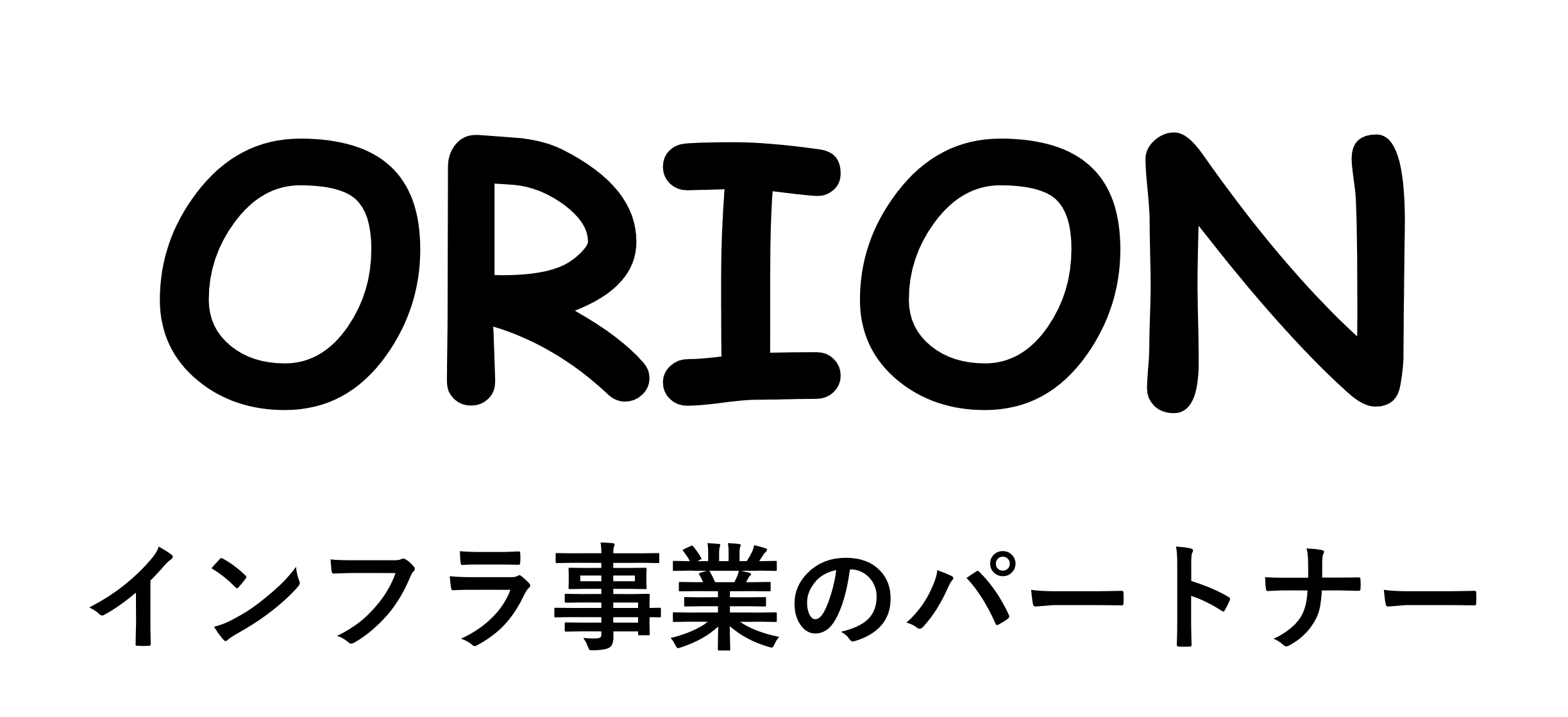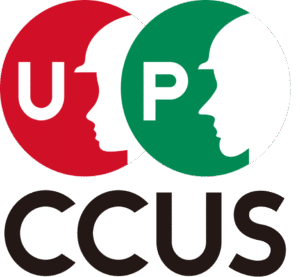建設業許可の必要なラインのひとつとして工事金額が500万円という基準があります。
いざ、工事金額が500万円を超えそうな場合によく聞く内容が「請負契約書を分割して1件あたり500万円に満たないようにすればいいですか?」という質問です。
確かに、1件の工事請負契約書において500万円未満であれば建設業許可は不要です。
Skip to Contents
関係法令 建設業法、建設業法施行令
建設業法第3条第1項第2号
「建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」は建設業許可が必要とされており、
建設業法施行令第1条の2
「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。」と、金額も定められています。
契約書は分割すれば問題ない?
結論から申し上げますと、違法です。
仮に、600万円の工事を請けた際に、契約書を300万円ずつで作成すれば一見許可が不要な工事に見えますが、建設業法上は契約書のみではなく実質的な判断がなされます。
つまり、300万円の2件以上の請負契約書であっても、総合的、実質的に現場、工期、発注者等が同一の内容であれば同一工事とみなされます。
このように、単に契約書を分割して許可が不要になってしまえば許可制度の意味を成しません。
いわば、何でもありの状態に陥りかねません。
罰則について
もちろん罰則も設けられています。
建設業法第四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
逮捕者も報道やネットニュースでも目にします。
罰則規定が設けられていますので、この処分を受けた際は建設業許可を取得しようとしても5年間は欠格要件に該当し、許可を取得することができなくなります。
そうならないためにも、建設業法はしっかりと遵守しましょう。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。